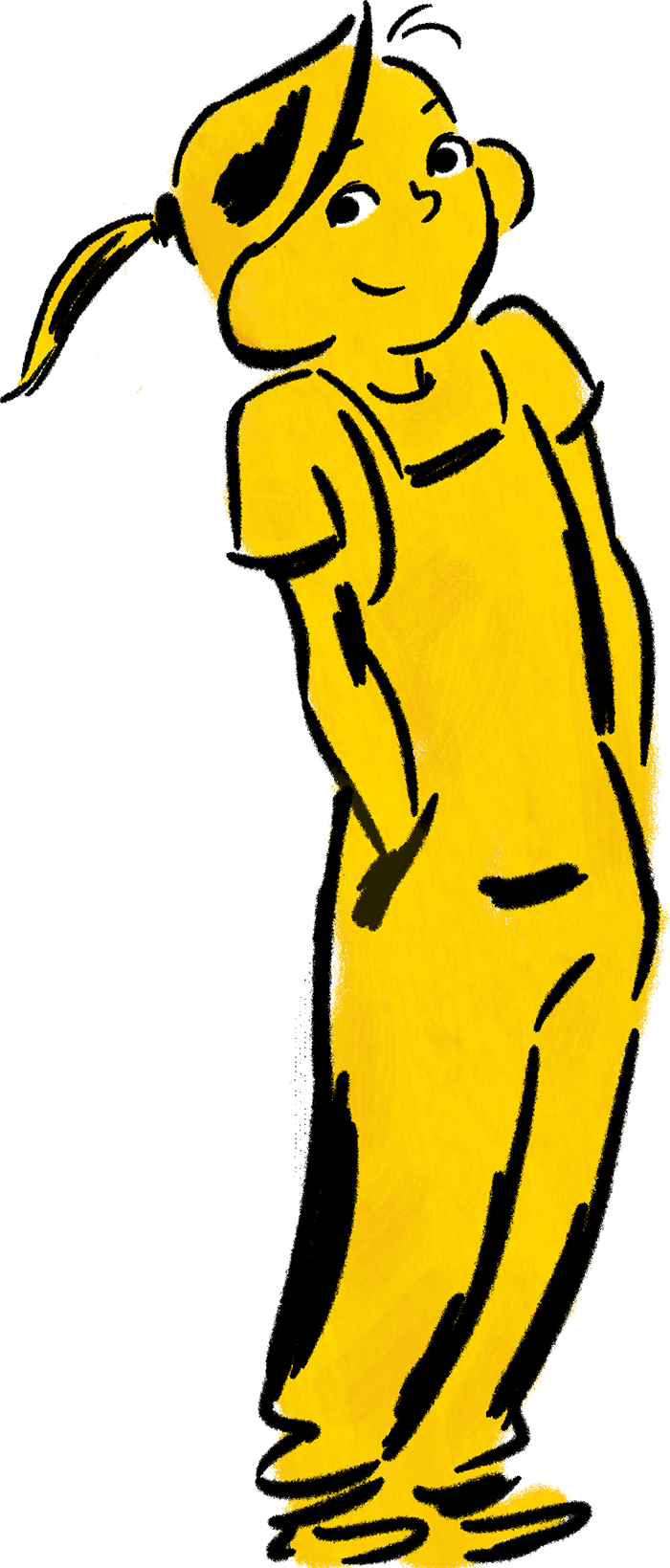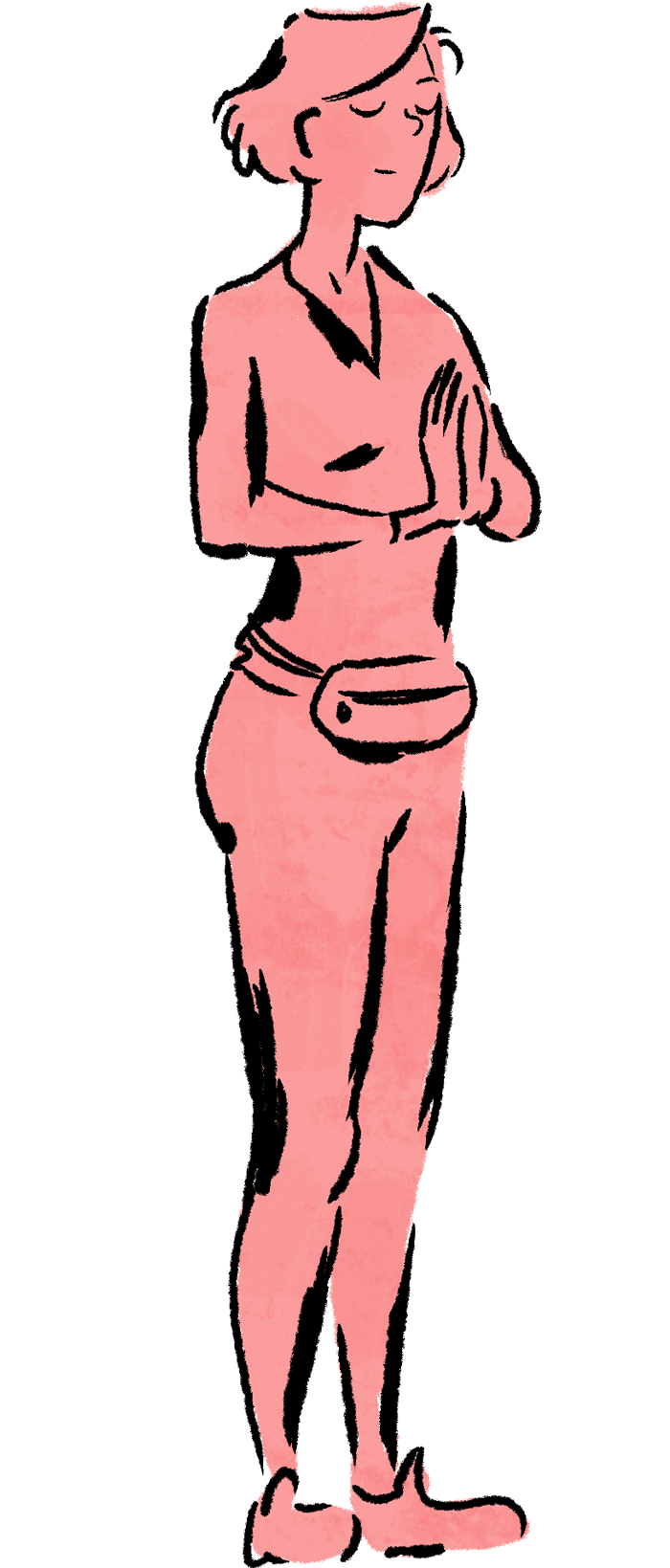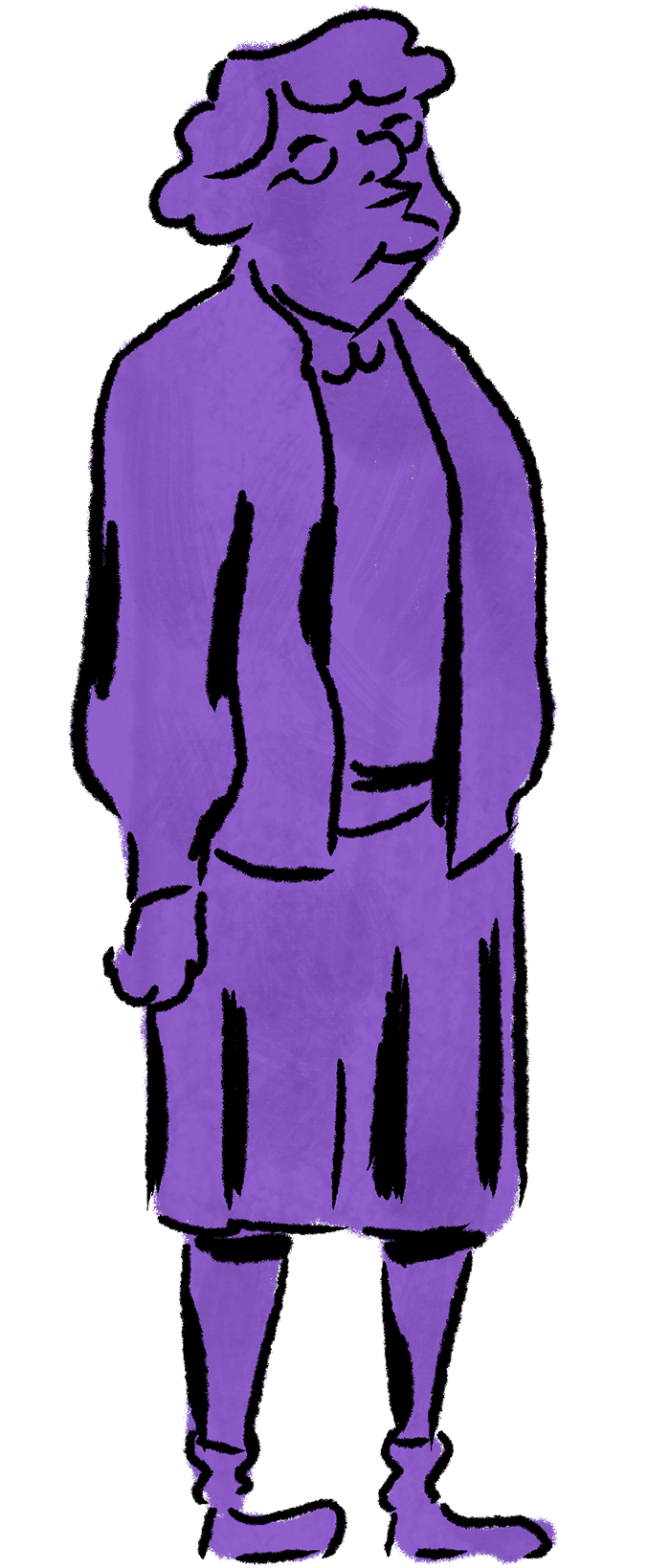『リンダはチキンがたべたい!』の原案は、キアラ・マルタが参加したムーランダンテのアーティスト・イン・レジデンスで生まれた。そこで余った2日間に、夫であり制作上のパートナーでもあるセバスチャン・ローデンバックと考え出した企画だ。二人の子を育てるなか、子どもに見せたいと思うアニメーションが少ないと思い、自分たちだからこそ作れる作品を考えた。
そのときにできたプロットは完成作とほぼ変わらないものだったが、制作のスタートまでに数年を要することになる。普通に作ろうとすると、かなりの予算が必要になりそうだったのだ。その後、ローデンバックが初の長編作品『大人のためのグリム童話 手をなくした少女』を完成させたことが、大きな転換点となる。ローデンバックが全編ひとりで作画したこの映画は、大胆な省略と躍動感を共存させるスタイルを採用しており、この手法を応用すれば、『リンダ』も「安く、かつ自由に」作りうると確信したのだ。
監督と脚本にはマルタとローデンバックの2人がクレジットされており、ほぼすべての作業を一緒に行った。「我々は夫婦ですし、お互いの作品でも協力し合ってきました」とローデンバック。「演出に対する考え方も同じです」とマルタが付け加える。本作の最もユニークな要素は、声の録音方法だ。絵づくりの「前」に録音されているのだ。マルタは「普通のアニメーションは絵に音を合わせますが、本作では音に絵を合わせるべきだと二人とも考えました」と言う。このやり方は、脚本の立ち位置を実写映画に近付ける。マルタは続ける。「実写の場合、脚本は“道具”であり、実際の撮影の現場で変わっていきます。本作はアニメーションですが、カオスを自由に描き切るために、実写的な即興性が欲しかったのです。即興を許しながら録音することで音にリアリティが生まれ、結果として絵のスタイルで冒険ができるようになりました。」
実際の“録音”風景は興味深いものだった。「実写映画の撮影とほぼ同じでした。カメラやカチンコがない以外は、スクリプターもいるし、俳優たちにもしっかりと演出をつけています」とマルタ。ローデンバックが続ける。「子どもにはおもちゃを持って演技してもらい、その音も入るようにしました。学校のシーンは学校で撮るなど、録音のロケーションも合わせています。」
声のキャストにも実写映画で活躍する俳優を起用した。「声そのものではなく、キャラクターを演じきる演技力を重視して選びました。」とマルタ。“カメラのない撮影現場”に対し、俳優たちに戸惑いはなかったのか。マルタは答える。「普段の仕事の延長でやれるので動揺はなく、カメラがないことで自分をきれいに見せることに気を取られず、むしろ演技に集中できていました。」
活き活きとしたキャラクターを生み出す秘訣は他にもある。主人公のリンダは二人の娘がモデルになった。マルタは言う。「パイロット版の制作時、娘はリンダくらいの年でした。イタズラ好きな性格で、彼女を観察することで、リンダにリアリティが生まれました。」ローデンバックは続ける。「リンダを演じたのは友人の娘です。生まれたときから知っていて、性格もリンダにピッタリでした。」
キャラクター造形については、シンプルさが重視された。スコット・マクラウドの『マンガ学入門』での「絵がシンプルなキャラクターほど、人の心に残りやすい」というテーゼに加え、実写映画でも『地下鉄のザジ』や『ペーパー・ムーン』のように、遠景でもしっかりと子どもが判別できるようなキャラクターの造形性を参考にしたという。
アニメーターたちにも「自由」が与えられる。本作はアニメーターたちによる集団作業で作画されたが、モデルシートに縛られる必要はない、録音から想像した動きを重視してほしい、と伝えたという。「現実の私たちは、状況によって顔が変わるものです。だから映画でもシーンによってキャラクターの顔が違っていい。アニメーターたちは本作における“第2の俳優”です。」
独特の色合いの背景美術はマルゴ・デュセニールが担当。マルタは言う。「彼女の本業は画家なので賭けではありました。でも、ガッシュで丸い点を散りばめながら描くスタイルは美しく、子どもたちに見せたいものができました」。デザイン面ではイタリアのデザイナーたちも“貢献”した。「ブルーノ・ムナーリの『ファンタジア』に影響を受けました。“もし赤ずきんが白ずきんだったら物語も変わるはず”というように、色とストーリーが直結するという考え方が面白い。レオ・レオニの『あおくんときいろちゃん』も、シンプルな色で子どもの世界を描く参考にしました。」
作曲家のクレマン・デュコルの功績も大きい。マルタは言う。「ストーリーと密接に関わる音楽を作りたかった。彼はまるでニーノ・ロータのように、映画の核に直結する音楽を作ってくれました。」音楽については象徴的なエピソードがある。終盤で流れるリンダのお父さんの曲は、歌詞の内容が悲しかったので、クレマンは最初、悲しいメロディーを書いてきた。「でも、それは私たちの意図とは違いました。『オール・ザット・ジャズ』のミュージカルシーンのように、歌われている内容は悲しいのに、映像や曲調はきらびやかで明るいというものが作りたかった。」マルタはこう言って話を締める。「私が育ったイタリアのコメディには笑いと涙が共存しています。今回の映画でも、その両方が重要だったのです。」